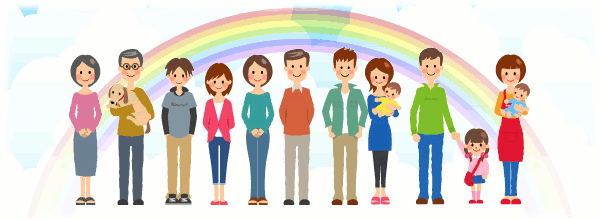つぶれない生命保険会社
つぶれにくい保険会社、つぶれても救済される保険会社とは?
生命保険は何十年と続ける可能性があります。その途中で保険会社が経営破綻したら困ります。
保険会社の経営健全性を判断する基準として、ソルベンシー・マージン比率や格付がありますが、実際に使ってみると、あまり役に立ちません。
そこで、このサイトでは「大きすぎてつぶせない」保険会社の選び方をご案内します。これも確実ではありませんが・・・
保険会社の経営リスクを判断する材料として、ソルベンシー・マージン比率や格付がよく上げられますが・・・
ソルベンシー・マージン比率や格付は、実際には役に立たないことが多いです。
ソルベンシー・マージン比率が役立つケースは限られる
ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金を支払う能力を%で表したものです。政府が決めた方法で生保各社が定期的に算定し、公表しています。
この数字が200%より低くなると危険と判断され、金融庁から改善を指示されます。
ただし、ソルベンシー・マージン比率が大きいほど安全性が高いというわけではありません。
ソルベンシー・マージン比率の限界
「比率が200%を上回った場合の評価であるが、比率で見られるため弊害が多い。高ければ高いほど健全という使われ方をするのは問題である。」
「ソルベンシー・マージン比率は、監督上の一つの指標に過ぎず、数値に絶対的な意味を持たせることは問題がある。健全性がこの指標のみで捉えられるものではない。」
金融庁第9回検討チーム議事録より
ソルベンシー・マージン比率が200%を上回っている保険会社を比較するとき、ソルベンシー・マージン比率の大小は、判定基準にはなりません。
そして、現在の生命保険会社のソルベンシー・マージン比率の平均は1000%を超えています。悪い会社でも500%前後です。
つまり、生命保険会社の経営安定性を比べるときに、ソルベンシー・マージン比率はあんまり役に立たない・・・ということですね。
格付は、差がつきにくい
格付というのは、企業評価を専門にしている格付会社による、保険会社のランク付けです。
ただし、かなり前から、朝日生命以外はA判定(=合格)という状況が続いています。あまり差がないので、比較しても判断に苦しみます。
同じA判定でもAAA+からA-まで幅があるので、勝敗を決めることはできますが、そこまでこだわる意味があるかと言うと・・・
格付会社は民間企業で、保険会社から依頼を受けて、その会社の格付を判定します。格付してもらうには、初期費用に加えて、毎年の更新料がかかります。
そのため、格付けを取得していない生命保険会社も少数あります。設立からまもなくて、まだ実績が乏しい会社とか・・・
国内で営業するすべての生保会社は、生命保険契約者保護機構に守られます。
生命保険会社が破たんすると、外資系であろうと、最近できた会社であろうと、わたしたち加入者は生命保険契約者保護機構の支援を受けることができます。
と言っても、破たん前とまったく同じ保障を受けられるわけではありません。
責任準備金の90%補償
保護の内容は、以下のように、保険業法等の法律で決められています。
- 原則として、破綻時点の責任準備金の90%が補償される。
- 通常より利率が高く設定されている保険は、90%より低くなる。
責任準備金とは、保険金等の財源として保険会社が積み立てるお金です。保険金や給付金そのものではありません。
破綻の後処理には2パターンある
ある生命保険会社が破綻したとき、その後の展開を大きく2パターンに分けることができます。
どちらのパターンでも、上でご説明した90%補償を受けられます。
ただし、保護対象でない部分は(利率とか計算方法とか)、新会社に移行するときに変更される可能性があります。
「大きくて潰しにくい」保険会社を選ぶという考え方もあります。
2008年にAIGグループ(米国に拠点を置く保険会社)が経営危機に陥ったとき、米国政府は大規模な支援をおこないました。
税金を投入することに批判はありましたが、つぶすことによる米国経済へのダメージが大き過ぎる、というのが当時の米国政府の判断でした。
日本では大手生保の破綻はまだありませんが、同じようなことが起こる可能性はあります。
加入者数が多い生命保険会社
加入者数が多ければ、破綻の影響はそれだけ大きくなります。
日本の市町村の中で最も人口が多いのが、横浜市の約370万人です。そこで、顧客数が370万人以上の生命保険会社を抜き出しました(2021年度)。
| 会社名 | 加入者数 |
|---|---|
| アフラック | 1,483万人 |
| オリックス生命 | 496万人 |
| かんぽ生命 | 939万人 |
| ジブラルタ生命 | 630万人 |
| 住友生命 | 687万人 |
| ソニー生命 | 399万人 |
| 第一生命 | 786万人 |
| 日本生命 | 1,224万人 |
| 三井住友海上あいおい生命 | 401万人 |
| 明治安田生命 | 715万人 |
メットライフ生命も370万人以上いると思われますが、数字を公表していないので省いています。
保有する有価証券が多い保険会社
保有する有価証券が膨大なほど、破綻すると市場への影響が大きくなります。
2020年度末時点の有価証券残高(一般勘定)が10兆円以上の生命保険会社をピックアップしました。
| 会社名 | 有価証券残高 |
|---|---|
| アフラック | 11兆6597億円 |
| かんぽ生命 | 55兆2745億円 |
| 住友生命 | 29兆7561億円 |
| ソニー生命 | 10兆1330億円 |
| 第一生命 | 32兆5302億円 |
| 日本生命 | 61兆5058億円 |
| 明治安田生命 | 34兆7042億円 |
| メットライフ生命 | 10兆5783億円 |
顧客数が多いとか有価証券残高が大きいのは、昔ながらの伝統的な生命保険会社です。
保険料は高くなりがちですが、その分安心感も大きいかもしれません。
もっとも、ここでお見せしている数字も現時点のものです。30〜40年後には変動しているかもしれません・・・
検討に使えるデータはいろいろあっても、結局、自分で決めるしかないのですね・・・
保険のプロに相談するなら、中立性が高く、商品を比較できるところを選びましよう。
わかりにくい保険だからこそ、中立な立場で助言してくれるプロに相談したいです。
保険ショップか独立系FP
保険を販売する人たちを、中立性と商品知識の2つの角度から分類したのが下の図です。
お勧めしたいのは、赤い文字の「保険ショップ」または「独立系FP」です。ここでの「保険ショップ」は、全国チェーンかそれに近い規模のものを指します。
| 保険ショップ |
|
|---|---|
| 独立系FP |
|
担当の人が公正な人柄で、勉強熱心であっても、こちらに勧めてくるのは自分が販売できる商品です。結局はかたよってしまいます。
また、販売できない商品については、保障プラン設計や見積作成の機会がないので、商品知識が深まりません。
できるだけ多くの保険会社の商品を取り扱えるプロに相談するのが無難です。
お勧めしたい保険のプロはこちら
保険ショップ・チェーンには、凄腕の営業マンだった人が設立した、営業色の強いチェーンが多いです。

そんな中、「保険見直し本舗」は、やみくもに店舗を増やすのではなく、サービスネットワークを丁寧に拡大させています。
FPを無料で紹介するサービス
家計のプロを認定する公共性の高い資格が、FP技能士(国家資格)やAFP、CFPです。そして、そんな家計のプロを無料で紹介してくれるのが、FP紹介サービスです。
このサイトでは「保険マンモス」をお勧めしています。

開始から20年に満たない若い業界ですが、「保険マンモス」はもっとも早くスタートしたサービスの一つで、実績を積み重ねています。